
明朝4時起床、7時、まだ暗い浜辺でボートの到着を待つ。
ハイコからは高速のボートでどんな荒波でも大丈夫だと聞いていたので、
クルーザー級の船がくるのかと期待していたが、闇の中から姿を現したのは、
粗末な木製のボートであった。こんなチャチなボートで
南太平洋の荒波を十数時間も進んで行くのかと思うと、
不安と心細さでMと二人、黙って顔を見合わせるばかりであった。
| 第一の目的地はワイゲオ島 木製ボートで荒波を進む |
|
木製のこのボートは、長さ15m、幅1.5m、中央部には1.5mほどの高さの屋根がついており、腰を45度に曲げないと歩けない。窓は両サイドにビニールシートが垂れ下がっているだけである。波が小さい時には、これを巻き上げて風を入れる。港を出るとすぐ、波よけのシートを両舷と前後まで降ろしてしまうので、中にいる我々はまるでビニールの温室というより、サウナ風呂に入っているようで、潮と汗とで全身ビチャビチャである。エンジンはヤマハの船外機45馬力が2基ついており、二人の船頭が立ちっぱなしで舵を取る。乗組員は我々にポーターと船頭を含めて6人であった。 我々の第一の目的地はワイゲオ島(Waigeo)であるが、この島は一風変わった地形をしている。いわゆるドーナツのような形をして高い山脈が連なっており、その一ヵ所のごく狭い部分が切れて外洋とつながっている。その湾には2本の川が流れ込んでいるため、部分的に水質が異なり、それぞれの水質に合った魚が生息しているらしい。 |

■現地には畑などない。漁労とサグーヤシが唯一の食料源だ |
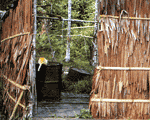
■当地で水は貴重品だ。写真は共同の水汲み場 |
今回は、その2本の川をそれぞれボートで行ける限界まで遡上し、その後は、原住民のカヌーを借りて漕ぎ、それでも動けなくなったら、ジャングルの中を行軍して上流に向かうという、相当ハードなスケジュールだ。 我々はサウナ風呂に入ったような状態のまま、洋上を5時間ほど航行すると、箱庭のような小島が見えてきた。この村には管理のポリスが駐在しており、了解を取らないと島の内部に入れないというので、持参の特別ビザを持ってご挨拶に上陸する。 ハイコが依然、初めてこの島に来た時は、かやぶきの家が2~3軒あったのみで、イギリスの探検家ウォーレスの百年も昔の風景記録と何一つ変わっておらず、時が止まっているようで大変感銘を受けた--と私たちに話していたが、今は少なくとも、人家は30軒は見受けられ、急速に俗化したことにア然としているようであった。しかし、子供たちは人なつっこいし、こんな島ならキャンプをするのもよいなぁと話し合ったりした。目的のワイゲオは、もうだいぶ間近である。 |
ひときわ高くなった波のシブキをかぶり、ボートは島と平行に航行しながら入口を探す。やっと入口が見つかった。本当に狭い。片方は絶壁が迫っており、水路は幅50mもあろうか。その間を抜けて湾に入る。あれほどガブッっていた船も嘘のように静かになり、水面を滑るように航行してゆく。
見渡すと両側の山の頂上近くには雲がかかっており、想像以上に山々が高いのに驚かされた。ビニールを巻き上げて風を入れられるので、サウナ風呂から開放されたようで心地よい。
快適な航行を続け、ボートは2時間ほどして、とある原住民の村を見つける。山と湾に挟まれたウナギの寝床のような村だ。ここでソーロンから頼まれて便乗した原住民の”おじいちゃん”が降りる。彼はこの村の村長であるらしい。彼を通じてカヌーを1隻と漕ぎ手の青年二人を貸してもらうことになった。
船は一刻の時間も惜しむようにすぐ出発した。何としても今日中に最奥部の川を見つけ、その上流の魚を調べるのだ。途中、4~5軒のカヤブキ家を見つけ上陸し、情報を集める。もう目指す川は近いらしい。しかし意外なことに、奥へ行くほど水はキレイになるのかと思っていたが、その正反対で水はどんよりと濁り汚れてきた。奥の方ほど外洋との水の対流がよくないためらしい。遂に目的の川を発見。ソーロンを早朝に出発してから約8時間も経過していた。
|
季節は乾期の最後頃になるのか、水が極端に少なく、ボートからカヌーに切り換える。30分も漕ぐと体力に限界がきた。しかしハイコは、「これからジャングルの中を歩いて上流の滝まで行くのでカヌーから降りてくれ」と言う。 その時の私とMのスタイルは、半パンツにゴム草履スタイル。とてもじゃないが、イバラとトゲだらけのジャングルなぞ歩けるものではない。彼らは、と見ると、ボートからカヌーに乗り換えた時、知らぬ間にチャッカリシューズを履き、長ズボンのジャングルスタイルに変わっている。彼にすれば、それぐらい自分で考えてやれ、と思っているのかもしれないが、ちょっと不親切である。これに似たことは今回の旅行中に随分とあった。我々の能力を高く評価してくれているのか、あるいは、自分本位なものの考え方をする人なのか、判断に迷うことが多くあった。 いずれにしても、草履スタイルでは無理なので私はあきらめ、一人カヌーでボートまで下り、3時間後に迎えにくるハイコらを待つことにした。 |

■サグーヤシの精製風景 |
帰ってきたMの報告によると、上流も水が少なく、ほとんどレインボーのみで、珍しい魚はいなかったらしい。しかし、中流付近で見られたグラスフィッシュは、通常輸入されるものと違い、骨格がしっかりしており、体はあくまで透明で肌にツヤがあり、さすが野性の持つ美しさは素晴らしかった、と感激していた。
道は、原住民がジャングル刀で切り開いてくれたらしい。ジャングルの中が相当ハードであったのは、私がMに貸した新しいゴム草履がボロボロになっていたのを見ても推察できた。
水のありがたさ 食物のありがたさ
|
日もだいぶ暮れかかってきており、早く下流へ下り、適当なキャンプ地を見つけねばならない。 カヌーと青年二人を借りた村(4、5軒のカヤブキ家があるのみ)へ、ヘトヘトになった私たちが着いたのは、午後8時頃であったろうか。船頭も早朝からほとんど飲まず食わずで、身ぶり手ぶりで空腹と渇きを我々に訴える。我々とて同様だ。一刻も早く水が飲みたい。人が住んでいるからには、必ず”真水”があるはずだ。 ようやくの思いで村の片隅に、山からの垂れ水が糸のようにトイからドラムカンにしたたっているのを見つけた。夢中で火を起こし、煮沸してから茶を入れて飲む。“美味い!” 先ほど冗談でMが「社長、今ここでコップ1杯の水を売ってくれるとしたら、いくらまで金を払いますか?」。「ウン、5千円までなら出そう。だけど1万円するというなら、もう少し辛抱するが」。「同感」などと言っていたのだが、二人が一万円でも買うと言い出したのは、それからすぐ後のことであった。そんな先程の冗談もウソのように、たらふく水をのんでホッとする。 |
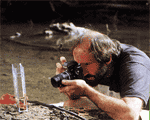
■採集した魚を撮影するブレハ氏 |

■採集した魚 |
真っ暗な舟着き場の方で何やらハイコと船頭たちがガタガタやっている。近づいてみるとなんとハイコは、「これから、すぐ2番目の川へボートを出せ!」と船頭に命令しているのだ。2番目の川へはまだ2時間もかかるし、無燈火の航行は危険だ。それ以上に「腹が減って動けない」と船頭は言う。 ハイコいわく、「我々は君たちの夕食の用意までしていない。何日かのジャングルの中のキャンプ生活になることは前もって言ってある。当然君たちが用意してくるべきで、我々には君たちの食事の心配までする義務はない。ぐずぐずいわず、今すぐボートを出せ!」 しかし、船頭たちはサボタージュを決め込んで、同行した青年の“カヤブキ家”に上がり込んで動く気配もない。ハイコは、と見るとフテクされてボートの屋根の上で寝ている。なんとかここでキャンプを張って泊まろうとハイコに勧め、シブシブ納得させた。 |

■原住民夫婦の住居
“人家のある所の蚊はマラリアに汚染されている危険があるので避けた方がいい”というのが本当の理由だという。彼の言うことも一理あるが、とかく彼のドイツ流の姿勢はトラブルを起こしやすい。その後もこのような彼の高圧的な態度でトラブルを度々起こし、難儀させられた。
やっとありついた食事(カップヌードル)も、Mはあまり食欲がないと言う。が、無理に食べさせる。石ころだらけの荒地を整理してテントを張る。寝心地は決してよくないが、すぐウトウトし始めた。Mが「社長、何やら動物が数匹テントの回りをうろついています」と言ったが、「放っとけ、放っとけ、ニューギニアには危険な猛獣はいないのだから」とすぐ寝入ってしまった。
とにかく1杯の水、1カップのスープのありがたみと貴重さを思い知らされた。1日目が暮れた。
