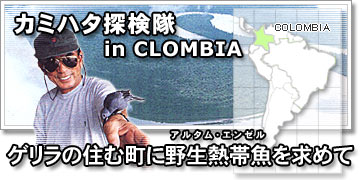
text & phot/神畑重三 協力/神畑養魚(株)
+++ Vol.2 +++
| 「ハードな旅になることは予測されていた・・・。」
コロンビアはコカインの密輸でも悪名が高く、治安の悪さも世界一だといわれている。 それだけに出発前から身の引き締まる緊迫感を覚えた。 当初からハードな旅になることは予測されていた・・・。 |
穴の開いたオンボロ機でジャングル上を飛ぶ
|
旅先で雨に降られるほど情けないことはない。コロンビアでは8~2月がベラノ(夏)と呼ばれる乾期で、3~7月がインブレルノ(冬)と呼ばれる雨期である。11月は乾期のはずなのに雨が降っている。もっとも、8~11月はインビルフィロ(小さな冬)と呼ばれて、週単位の雨期が何回かあるらしく、川での極端な水位の変動は11月まで見られないとのことだ。ちょうどこの小雨期に当たったみたいで、今後の旅が心配になってきた。 |
 ■蛇行する川とはまさにこのこと |
 ■よく見ればブリキ張りのおもちゃのような飛行機 |
 ■ビヤビセンシオ空港よりイニリダは向かう約3時間半のフライト |
雨は1時間ほどで小降りになり、やっと搭乗したが、乗り込んでその驚きが倍になった。これまでもいろんな機会に小型機をよく利用してきたが、こんなオンボロ機は初めてだ。シートベルトは根元でぷっつりと切れ、シートもぶっ壊れている。こんなポンコツで3時間半も飛ぶのかと思うといっそう不安がつのるが、いまさらどうすることもできず、運を天に任すしかあるまい。
それでも何とか離陸した機は快調にぐんぐん高度を上げていく。下は緑一色の大平原である。ところどころに大きな影絵のような黒い模様が見える。野火による焼け跡らしい。まるでピカソの絵のようで、大自然が地表に描いた一大パノラマ画である。
足元がチカチカ光るので、ふと床を見ると、足元の鉄板が虫食い状にぽつぽつと穴が開いており、下界が丸見えだ。足元から下界が見えると、とてつもなく恐ろしい。この薄っぺらな鉄板1枚の下に1000メートルからの空間があるのかと思うと、忘れていた高所恐怖症がいっぺんに噴き出して、あわてて荷物で穴をふさいだ。
膝の上に何やら冷たいものが上から落ちてきた。機が雲の中に入り、天井からぽつぽつ雨もりがしてきたのだ。パイロットが私の心配を感じとってか、「機体は10年前の型だが、エンジンは新しくて、まだ100時間しか飛んでないから大丈夫だ。それにイニリダへ行く途中のジャングルには不時着用の場所が2ヵ所もあるから心配しないでいいよ」と、余計に心配になることを言う。
天候が急変した場合、積み荷を減らすために荷物をぽんぽん投げ落とすらしいが、最初に犠牲になる荷物は魚箱だという。魚にはとんだ災難だが、人命を救うためなら仕方ないだろう。
およそ1時間半ほど飛んだころから下界の景色が急変した。ゴルフ場のような大平原を過ぎ、ジャングル地帯に入ったのだ。大きく蛇行する川とその支流、そして湖など、ニューギニアで見慣れた光景に似ているが、何度見ても飽きることのない大自然のスペクタクルだ。地球は狭くなったというものの、やはり「でっかい!」というのが実感だ。
ジャングルの真ん中にぽつんと赤茶けた地面が目に入ってきた。目的地のイニリダだ。人家もあるようだ。さあ、着陸だぞ。機は大きく旋回しながら、原野の中の赤土滑走路に無事ランディングした。一瞬ほっとして、体中の緊張感がいっぺんに解凍されていくのがよくわかる。小型機での3時間半のフライトはけっこうしんどい。
突然、機がガクンと急停止した。前輪が泥のぬかるみに突っ込んで動けなくなったのだ。機長の要請で、全員が機から降りてエンジンを全開にして後押しするが、尾翼側がすぐ上がってなかなか離脱できない。とうとう土地の人を応援に引っ張りだして、何とか泥の中から脱出できた。
機長が「あなた方がジャングルから帰ってくるまで4日でも5日でもここで待つ」と言う。インディオ出身の彼はジャングルの中の親戚の家に泊まるのだそうだ。文明の利器を操るパイロットが茅葺きの家で寝泊まりするとは・・・・・・おかしくて思わず吹き出してしまった。
出荷場では、兵士が自動小銃を手に警備
|
空が抜けるように青く澄んでいる。しかし、猛烈に暑そうだ。迎えのトラックで町に入って、とりあえず軍の駐屯所に滞在許可を貰いに出向かいた。町角のところどころに肩から自動小銃を下げた若い白人兵士が警備のために歩哨に立っている。国境近くの辺境の町のせいなのか、異様なほどものものしい警備ぶりに驚く。若いコマンダーがいろんな質問をするが、最後には「よい滞在を」と快く送り出してくれる。外国人としてここに入ったのは三十年ほど前にドイツ人が一人だけいたそうで、むろん日本人はわれわれが初めてである。 この国に来て中国人が一人もいないことにちょっと不審を抱いた。世界のどこににでも見かける中国系の人が一人もいないのを不思議に思っていたら、「国の方針で昔から中国人の入植を認めなかった」とラフェエロが黄色人種のわれわれを気遣って、ちょっときまり悪そうに口ごもった。コロンビアの人種構成は全人口3000万人のうち六割がメステソ(インディオと白人の混血)で、残り4割の内訳は白人とインディオが半々だそうだ。 イニリダの人口は約9000人で、そのうち半分がインディオ、45パーセントがメステソ、残り5パーセントが白人だという。イニリダの町はイニリダ川水系の中心地にあり、流域に点在するインディオ部落から持ち込まれたものが集積されている。主たる産物は、食用魚、ヤシの繊維、熱帯魚などである。インディオたちはカージナルやアルタム・エンゼルなどを魚の採集業者に売って換金し、日用雑貨品を仕入れて村へ帰っていくのだそうだ。彼らにとって熱帯魚の収集は生きていくための大切な産業なのだ。 町のはずれにある魚のストック場に赴いてみると、コンクリートのタタキ池にアルタム・エンゼルが数百尾もいて、「わあ、凄い!」と思わずため息が出た。箱にはいったビニール袋にはカージナルがうじゃうじゃ詰まっていた。インディオたちにはビニール袋が貸与され、とった魚を袋に入れてここに持ち込み、酸素を入れてボゴタまで空輸するが、飛行機に積み切れなかった余分が次の便までここでストックされているのだそうだ。 カージナルやアルタム・エンゼルの人工繁殖はまだ世界で誰も成功していない。いまのところ、いおれらの魚はアゾン水系に棲む野生魚に頼るしかないが、日本の熱帯魚屋さんの水槽で泳いでいるこの種の魚は、この辺境の地のインディオたちに採集され、危険なジャングルの上を飛んで、幾人かの業者の手を経ながら、ボゴタから地球を半周して、はるばる日本まで運ばれてくる。一尾の魚のバックグラウンドを考えると、なまはんかな気持ちでは魚を扱えないと痛感した。殺さないように大切に飼いたいものだ。 |
 ■昼日中、ゲリラの襲撃を警戒して熱帯魚屋の中まで兵士が警備  ■イニリダの街の中、ゲリラ警戒の駐屯兵の望楼、近くのジャングルの中にはゲリラが住む  ■イニリダ川でとれた熱帯魚の集積所。ここからパッキングして小型機でビヤビセンシオへ。そこからコカイン街道を通ってボゴタの空港へ |
